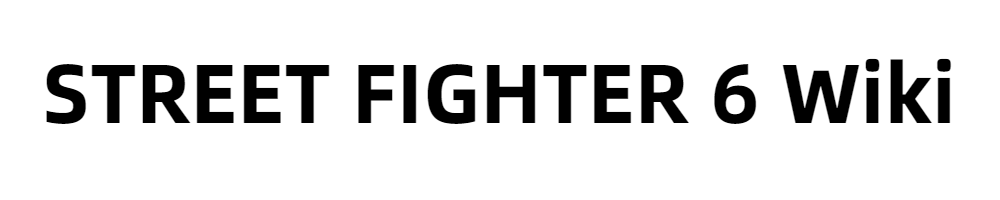#author("2023-06-05T04:36:03+00:00","","")
*公式・システム用語 [#ia63e8a5]
-ハードダウン
--通常のダウンとは異なるダウン状態。~
ダウンした直後に何も操作しないとその場で起き上がる通常起き上がりを取り、タイミング良く2個以上のボタンを押す(連打でも可)と後方に転がりながら起きる後方起き上がりを取るようになっている。~
そして、一部の技は受けた後に画面横に「HARD KNOCKDOWN」と表記されるが、この場合はその場受け身しか取ることができない。そのため、ハードダウンを取った側は起き攻めが容易になる。
--主に投げ技でパニッシュカウンターを決めた場合、SA3やCAを決めた場合に発生する。
-CROSS-UP
--相手に裏回りながら攻撃することを指す。日本語では「めくり」と呼ぶ。
--格闘ゲームのガードは原則「後ろ(相手がいる方向と逆)に歩いている状態で攻撃を受けると立ちガードになる」という原理なのだが、ストファイシリーズでは「相手が背後にいると、その瞬間にガード入力の方向が逆になってしまう」仕様があり、これを使ってガード入力を解かせて攻めを通すことが可能となっている。
--これを駆使した正面からの攻撃と裏回りつつの攻撃でいわゆる二択をかけることが可能。本作ではドライブパリィで両対応できるものの、相手がそれをするようになったらこの二択にいくフリをして投げ、などが通るようになるため俄然強力。
--ちなみに以前からの格闘ゲーマーからはたまに「裏択」と呼ばれることもある。
*非公式用語 [#cf69be33]
**略称 [#kdbeb5e0]
-SF
--ストリートファイターの略称の一つ。
-ストファイ
--ストリートファイターの略称の一つ。
--以前からある略称であると同時に、どういう訳か%%「ニワカ」っぽさを感じさせるという理不尽な理由で%%揶揄されがちな略称でもある。
-スト6
--本作ストリートファイター6の略称の一つ。読み方は「ストシックス」だったり「ストロク」だったりで人によりまちまち。
--かつて爆発的なヒットを記録した「ストリートファイター2」が「スト2(ツー)」と略されていたのにちなんで、ストリートファイターシリーズは各ナンバリングごとに「スト〇」といった略称を与えられるのがお約束となっている。
-OD
--オーバードライブのこと。
--過去作の類似システムである「EX必殺技」の略称「EX」で通じる機会も多い。
-SA
--スーパーアーツのこと。
--また、ゲージ1本を消費するSAはSA1、2本だとSA2、3本だとSA3といった表記を使われる場合がある。
-CA
--クリティカルアーツのこと。
--前作ではあくまでゲージを全放出して繰り出す大技の総称だったが、本作では「HP残量が25%以下で強化されているSA3」の名称に用いられている。
-Dリバ
--ドライブリバーサルのこと。
--また、前作スト5のよく似たシステム「Vリバーサル」の略称「Vリバ」、あるいはガードキャンセルを略して「ガーキャン」で通じる事もある。
-ジャスパ
--ジャストパリィのこと。
-パニカン
--パニッシュカウンターのこと。
-昇竜
--主には昇龍拳のこと。また、昇龍拳と類似した特徴を持つ技も伝わりやすさ・変換しやすさ重視でこう呼ぶこともある。
**SF6用語 [#je867744]
//SF6界隈で独自に使われる用語
-上のゲージ、下のゲージ
--上のゲージとはドライブゲージのことであり、下のゲージとはスーパーアーツゲージのこと。
-レベル1・2・3
--各種スーパーアーツのこと。SAゲージの使用量によって技が変化し、それらに区別をつけるためにこのような名称が使われる機会がある。
--過去にカプコンが開発した格闘ゲーム「ストリートファイターZERO」シリーズや「マーベルvsカプコン」シリーズなどの超必殺技にも同様の仕組みが用いられており、それが当時からのプレイヤーに流用されたものと思われる。
**格ゲー用語 [#je786bab]
//ストリートファイターシリーズ及び格闘ゲーム全般で広く使われる用語をまとめていく。
-テンキー表記
テンキーとはPCなどの数値入力用のキーボード。(下記のような数字の配列)~
~
789~
456~
123~
~
大昔は斜めの矢印が「機種依存文字」という扱いだったため、格闘ゲーム界隈では、長きにわたりコマンド入力の表記をこれの数字で代用する文化がある。~
例:↓↘→+強パンチ : 236強P~
偶に↓\→と斜線を利用しているサイトもある。
-足
--「足払い」の略。主には当てれば即相手を転ばせてダウンさせるしゃがみ強キック攻撃をこう呼ぶ。
--モダンタイプでは特殊技(レバー入れ通常技)として出せる場合がある。
-小、中、大
--各種ボタン強度を指す弱・中・強の亜流。
-コア
--しゃがみ弱Kのこと。しゃがみ弱Kを表す「小足払い」が「小足」→「こあし」→「コア」と変化していったもの。
--上記するように、「足」とはあくまで「足払い≒しゃがみキック」を意味する用語であるため、立ち弱Kを「立ちコア」、しゃがみ中Kを「しゃがみ中足」などと呼ぶのは厳密には誤用。
-コパ
--しゃがみ弱Pのこと。
-屈
--しゃがみ状態のこと。
-暴れ
--不利な状況でもお構いなしに攻撃を繰り出すこと。
--有利状況であることを良いことに強気な攻めを仕掛けてくる相手に対して逆に反撃できる。~
ただし、この暴れを相手に読まれていた場合、有利状況である事を活かしてこちらの暴れに対して一方的に打ち勝てる技を繰り出す「暴れ潰し」を受けるリスクがある。
-置き、置き技
--相手が動いた所に引っかかるよう、こちらから技を先出ししておく動きのこと。
-起き攻め
--相手を吹っ飛ばしてダウンさせた後、キャラクターが起き上がってきた瞬間を狙って更に攻めを仕掛けること。
--起き上がり動作自体は完全無敵のため手出しできないものの、攻撃を決めた側と受けてダウンさせられた側では硬直差で攻撃側が大きく有利となる事が多く、その硬直差を活かすことで強力な攻めを仕掛けることができる。
-画面端
--それ以上進むこともスクロールされることもない、ステージの両端に聳える透明な壁のこと。
--この画面端を相手に背負わせることに成功すると、それ以上相手は後ろに下がれないためこちらが一方的に距離を詰める事ができる。また、相手は下がれない一方で自分は下がる事ができるため、これを活かして地上戦の駆け引きでも有利な読み合いができる。~
また、相手がそれ以上下がる事がないという性質を利用することで、通常では決められないコンボを決める事も可能。
--逆に相手に端に追い詰められてしまうと、上記した優位性を相手から押し付けられる形となる。
--本作SF6は全体的な設計として過去作以上にこの画面端での攻めが強力なバランスとなっており、効率よく対戦相手を画面端に追いやり、逆に自分は画面端に追いやられないようにする戦略が勝率に直結する。
-火力
--ゲーマー界隈では、「攻撃力の高さ、与えるダメージの高さ」といった意味合いで広く使われる。
-切り返し
--主には「暴れ」すら通らない高密度の攻めに対し、無敵時間がある技を繰り出すことで対処する行動のこと。
-グラップ
--投げ抜けのこと。過去シリーズのストⅢ3rdで同様のシステムが「グラップディフェンス」と呼ばれており、これの略称がそのまま使われる機会がある。
-硬直差
--お互いのキャラクターが技やガードのモーションで硬直状態となった後、先に動けるようになった側と後から動けるようになる側のタイミングの差をフレームを用いて具体的な数値に落とし込んだもの。
--硬直差は±と数字を用いて表記される。例えば、自分が1フレームだけ早く動けるようになる状況の時は「+1」、逆に相手が1フレームだけ早く動けるようになる状況の時は「-1」といった要領。
-差し返し
--中距離で相手の牽制技等を空振りさせ、その隙を狙ってこちらの技を当てに行く一連の動きのこと。
--主には相手の技が目の前で空振りしたところにパニッシュカウンターを取れている時の動きをこう呼ぶ。
-仕込み
--主に、立ち回りで振られる通常技にキャンセル必殺技まで入力しておくこと。
--本作に限らず多くの格闘ゲームのほとんどのキャンセル可能技は、「ヒットorガード時のみキャンセル可能(空振り時はキャンセルできない)」という仕様がある。~
そのため、敢えて空振りする距離で振られる通常技にはその後のキャンセル必殺技まで入力しておくことで、空振りした時は通常技のモーションを空振りするだけで済み、相手が前進するなどの理由で通常技に当たっていた場合はキャンセル必殺技までが出て自動でコンボにすることができる。
--毎回仕込むのはかなり手元が忙しくなり、また入力が遅いと通常技空振り>最速で必殺技といった形で出てしまうのが難しいところ。また、高レベルの対戦では前歩き→即ガードといった動きで通常技をガードしにいき、キャンセル必殺技を出させて反撃するといったテクニックが用いられる事もある。
-シミー
--主には「投げ抜けを誘って空振りさせ、その隙を確認して隙を取る」一連のプレーのこと。
--投げを空振りするモーションが「投げシケ」と呼ばれており、「投げシケを狩る動き」といったニュアンスと思われる。
--本作では投げシケを狩るとパニッシュカウンターを取ったことになるので重要度が増している。
-対空
--相手のジャンプ(飛び込み)に対し、こちらの攻撃をぶつけて迎撃すること。
--ストリートファイターシリーズでは一旦ジャンプすると基本的に着地するまで無防備な状態となり、ガードなどの防御行動が取れない。このため、上に対して判定が強いしゃがみ強Pや、ジャンプ攻撃に対して無敵となる昇龍拳などを用いることで確実なダメージを与えるチャンスとなる。
-弾
--飛び道具のこと。
-中段、中段技
--しゃがみガード不能(立ちガードは可能)の性質を持つ技のこと。ほとんどのジャンプ攻撃と、一部キャラクターの特殊技・必殺技がこれに該当する。~
大抵のものは上から被さる、拳や踵を真下へ叩きつけるようなモーションを取るため、慣れてくると直感的にも分かるようになる。~
対義語は下段。
--「SF」シリーズは基本的に下段に素早く隙の少ない技が多い。そのため、相手に近づかれたら下段を警戒してしゃがみガードで守りを固めるのがセオリーとなり、その際に裏をかく形で中段攻撃を放つとヒットしやすい。
--余談だが、語源は恐らく3D対戦格闘ゲームである『バーチャファイター』シリーズから。当作では上段(取り回しが良いが、打点が高すぎるためしゃがまれると当たらない)技、中段(しゃがんでいる相手にはガードされず、立っている相手にも空振りする心配はない)技、下段(立っている相手にガードされないが、しゃがみガードされると大きな隙を晒す)技といった形で各打点に特徴が与えられており、言いやすさから「しゃがみガードできない技」を指す用語として『SF』界隈にも輸入され現在に至るまで定着している。
-飛び込み
--主には前ジャンプで相手の真上に覆いかぶさっていく動きのこと。
-安全飛び込み、安飛び、セーフジャンプ
--主に起き攻めの状況で、相手に無敵技を出されてもガードが間に合うタイミングでジャンプ攻撃を繰り出す事。
--相手の起き上がりタイミング丁度に最も低い高度からジャンプ攻撃が当たるようにすると、相手がガードなどをしていた場合は起き上がった瞬間にジャンプ攻撃が当たり、相手が無敵技を出していた場合は着地モーションでジャンプ攻撃の隙がキャンセルされてガードが間に合うようになる、といった原理。
---以前は「ガードもできる詐欺臭い攻撃」というニュアンスで「詐欺飛び」と呼ばれていたが、「詐欺」という単語の悪さから変更された歴史がある。本サイトでも昔からの人がうっかり詐欺と書いていたら、編集してもらえると幸いである。
-反撃確定、反確
--大ぶりな技をガードされたり空振りしたりした後、技のモーションが終わる前の段階に攻撃を叩き込まれること。
--技のモーション中は当然ガードができないため、確実に攻撃がヒット(確定)してしまう。
--やらかして反撃される方が「反確」、逆に反撃を叩き込む方は「確反」という。
-フレーム
--略して「F」とも。ゲームを形作る時間構成のこと。多くのゲーム作品では、1秒=60Fで構成されている。
--格闘ゲームではキャラクターの動きや技の速さ/遅さを具体的に数値化するためにフレームを用いられる。~
-無敵技
--攻撃モーション中に無敵(相手の攻撃に当たらない)時間がある技。OD版の昇龍拳や各種SA(Lv3)などが該当。
--相手の技とかち合いさえすれば一方的に勝てるため非常に強力だが、その代償としてガードされると痛い反撃を受けてしまう技やそもそも繰り出す上でドライブゲージやSAゲージといったリソースを要する技が大半。
-リーサル
--相手の残り体力を0に至らしめる、トドメの一撃及びそこから繋がっていくコンボのこと。~
英単語の「lethal」が由来で、「致死の」「決定的な」といった意味がある。
--高レベルな対戦では相手の残り体力を計算しつつ、ドライブゲージやSAゲージをありったけ用いた大ダメージコンボを決めることで一気にラウンドを取りに行く場面があり、そういった判断を取ることを「リーサル判断」などと呼ぶ。~
もちろん決着ラウンドの時はいいのだが、まだラウンドが残っている場合、ゲージを吐いて倒した場合次のラウンドはゲージ不利状況から始まるので、どんなときでもリーサルコンボを決めていくというのは考えた方がいい。
--似た用語で「倒し切り」「殺し切り」などがある。
**ネットスラング [#g6c56364]
当然だが公式用語ではなく、ものによってはかなり俗な表現もあるので使いどころに注意。
-スト66
--攻勢時におけるドライブラッシュの重要性が非常に高いが故、前>前の入力(テンキー表記でいう6>6)を伴う機会も非常に多くなるスト6のゲーム性を揶揄したもの。
-柔道
--格闘ゲーム(特に前作『スト5』)界隈では、「投げ技を決めた後に相手の起き上がる瞬間に再度投げを狙い続けることで、相手が起き上がり際に投げ抜けやバックステップをしない限り投げによる攻めが半永久的にループする」ことを指す用語。
--特に前作『スト5』のシーズン1における、リュウが背負い投げを何度も決める様子を指すものとして有名。
--『スト5』ではその後の調整で全体方針として柔道がなくなっていったが、本作では画面端でのみ決められる攻めパターンとして復活(一部例外キャラクターあり)。この柔道の存在もまた、「スト6は画面端の攻めが強い」と評される理由の一つとなっている。
-体験
--R5年4月21日以降より配信された、本作スト6のデモプレイver(体験版)のこと。
--使用可能キャラクターはリュウとルークのみで機能も大幅に制限されているながら、製品版発売の1か月以上前から無料で配信され、何よりオフラインであれば対人戦までできるというかなり太っ腹なサービス内容がユーザーに鮮烈な印象を与え、「体験」という言葉が一種のキーワードと化した。
-8先生
--本作のCPULv8(最高レベル)のこと。8の読み方は普通に「はち」と呼ぶ人もいれば、「エイト」だったり「レベハチ」だったりで人によりまちまち。~
本作のCPUは過去作のものと比較しても非常に完成度が高く、人間の強豪プレイヤーにかなり近い動きを取ってくる。そのため、格闘ゲーム初心者にとっては模範的な動きの参考資料として、上級者にとっては程よいスパーリングパートナーとして幅広いプレイヤーにとって非常に頼もしい存在となったため、畏敬の念を込めて「先生」と呼ばれるようになった。
-闇の戦士
--プレイヤー界隈において何かと「闇」が深い、恐れられているキャラクター達のこと。%%早い話が「クソキャラ」とほぼ同義。%%~
--現状はエドモンド・本田、ブランカ、ザンギエフ、ダルシムのことを指すが、~
中でも上記4人は格闘ゲームというジャンルそのものを開拓した『ストⅡ』から参戦している由緒正しき面々故、公式からはSFシリーズ通して丁重に扱われる傾向にある。~
一方で、ビジュアル・性能ともに良くも悪くも非常に「濃い」キャラクター達でもあるため、プレイヤー界隈では揶揄の対象となってしまうのが一種のお約束と化している。